
最近、WEBやSNSで「月1万円~不動産投資ができる」「相続税対策に有効」などという謳い文句の「不動産小口化商品」の広告を目にしたという人も多いのではないでしょうか。そのような広告を見ていると、少額から手軽に不動産投資を始められて、メリットが多いように感じてしまう不動産小口化商品ですが、近年「トラブルがあった」「危険だ」という噂も聞こえてきます。
本記事では、不動産小口化商品とはどんな商品なのかに加えて、そのメリット・デメリットや現物不動産投資やREITとの違いについて解説します。
投資における失敗を避ける鉄則は、よく商品の特徴を理解し、似た商品とよく比較検討したうえで、最も自分のニーズや許容できるリスクにあった商品を選ぶことです。本記事を参考に適切な投資判断を行ってください。
不動産小口化商品とは?

まず、不動産小口化商品とはどのような商品なのか、その仕組みや種類について解説します。
不動産小口化商品の仕組み
不動産小口化商品とは、一棟マンションやビル、商業施設など大規模な不動産を1口1万円~数百万円程度に分割して、不動産特定共同事業法に基づいて販売されている商品です。
運用会社が物件選定を行い、投資家が出資した金額に応じて、賃料収入や売買益が分配されます。
多くの投資家から出資を募り、不動産に投資し、その収益を分配するという点で、金融商品取引法を基に販売されているREITに似た仕組みの商品といえるでしょう。
近年では、類似商品として、不動産クラウドファンディングなども登場しています。
不動産小口化商品の種類
不動産小口化商品は大きく「任意組合型」「匿名組合型」「賃貸型」の3種類に大別できます。
任意組合型の不動産小口化商品は、長期運用を前提とするものが多く、相続税対策になるなどの点で現物不動産投資との共通点が多いのが特徴です。
一方、匿名組合型の不動産小口化商品は、1口数万円程度の少額から投資でき、運用期間が比較的短いものが多いというREITに似た特徴があります。
賃貸型は複数名の出資者が共同で購入した不動産を不動産会社に賃貸するもので、不動産登記簿に出資者の名義で登記されるなど、現物不動産投資に最も近い特徴を持ちます。ただし、販売されている賃貸型の不動産小口化商品は少なく、出資金額や運用期間は商品によって異なりますが、任意組合型と同程度のものが多いようです。
3種類の主な違いは下記の表のとおりです。
| 任意組合型 | 匿名組合型 | 賃貸型 |
事業主体 | 組合員(出資者) | 営業者(事業者) | 不動産会社 |
出資金額 | 100万円程度~ | 1万円~ | 商品による |
運用期間 | 10年~ | 数ヶ月~10年 | 商品による |
不動産の所有権 | 〇 | × | 〇 |
所得区分 | 不動産所得 | 雑所得 | 不動産所得 |
損益通算 | 〇 | × | 〇 |
相続税対策 | 〇 | × | 〇 |
責任の範囲 | 無限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
不動産小口化商品と現物不動産投資の違いとは?

前述のとおり、不動産小口化商品(任意組合型・賃貸型)と現物不動産投資には、「相続税対策になる」「不動産所得として申告し、損益通算ができる」など多くの共通点があります。一方で、明確に異なるポイントも多くあります。両者の違いを見ていきましょう。
不動産小口化商品のほうが投資金額が少額
現物不動産投資の場合、割安な中古不動産でも1,000万円程度するものが一般的です。一方で、不動産小口化商品は1万円~数百万円程度で不動産に投資することができます。
現物不動産投資のほうが投資の自由度が高い
どちらも投資家が投資対象を選べるケースが一般的ですが、不動産小口化商品は物件の管理を任せる不動産管理会社や売却時期を投資家自身で自由に決めることができません。また、不動産小口化商品よりも現物不動産のほうが多く市場に流通しているため、多くの選択肢の中から自分にあったものを選ぶことができます。これらの理由により、現物不動産投資のほうが、自由度が高い投資といえるでしょう。
現物不動産投資は借入を利用できる
現物不動産投資では、一般的に投資用マンションローンやアパートローンなどを利用することができますが、不動産小口化商品の場合は原則借入を利用することはできません。そのため、余裕資金が少ない人やレバレッジを効かせて投資をしたい人、住宅ローンに付随する団体信用生命保険を活用して効率的に保障を準備したい人には、不動産小口化商品は向かないでしょう。
不動産小口化商品とREITの違いとは?

次に、不動産小口化商品(匿名組合型)とREITの違いについて解説します。
REITは投資対象の不動産を投資家が選べない
REITは不動産投資法人がどの物件に投資するか判断するため、どんな不動産に投資するかは選べません。一方で、不動産小口化商品の場合は、もともとどのような不動産に投資するのか明記して募集されることが一般的なため、投資家が投資対象を確認したうえで商品を選ぶことが可能です。
不動産小口化商品は流動性が低い
不動産小口化商品は運用期間中に換金できないものが多いため、流動性が極めて低いのが特徴です。一方で、REITは証券取引所の取引時間内であればいつでも売買できるため、余裕資金が多くないけれど、不動産に投資をしたいという人にはREITのほうが向いているでしょう。
不動産小口化商品は相続税対策に有効
REITの相続税評価額は、現金や株などと同様に「時価(相続開始日の終値等に準ずる)」を基に算定されるため、REITを保有しているだけでは相続税対策にはなりません。
一方で、不動産の所有権のある不動産小口化商品(任意組合型・賃貸型)の場合、相続税評価額が時価の70~80%になるため、一定の相続税の節税効果が期待できます。
REITは配当所得、不動産小口化商品は不動産所得または雑所得
不動産小口化商品は前述のとおり、不動産特定共同事業法に基づいて販売されている商品ですが、REITは金融商品取引法に基づいて販売される投資信託の一種です。
いずれも、利益に対して課税される点は同じですが、所得区分や税率が異なります。
それぞれの所得区分・税率は下記の表のとおりです。
| 所得区分 | 税率 |
REIT | 配当所得(分離課税) | 約20% ※iDeCoやNISA口座で運用する場合は非課税 |
不動産小口化商品(賃貸型・任意組合型) | 不動産所得(総合課税) | 約15~55% |
不動産小口化商品(匿名組合型) | 雑所得(総合課税) | 約15~55% |
不動産小口化商品のメリットとは?

不動産小口化商品のメリットについて解説します。
少額から不動産に投資でき、分散投資に向いている
不動産小口化商品には1万円程度から出資できるものもあり、少額から不動産に投資したい場合や分散投資に向いています。
ただし、少額から不動産に投資する方法にはREITもあるため、投資判断をする前に、それぞれのメリット・デメリットや違いをよく理解するよう努めましょう。
相続税対策に有効
前述のとおり、不動産小口化商品(任意組合型・賃貸型)を活用すると、相続税評価額が時価の70~80%になるため、現金を不動産小口化商品に変えることで相続税対策になります。
さらに、口数ごとに分割して相続することができるため、相続人が複数いる場合に分けやすいのもメリットです。
ただし、相続税対策としては、現物の投資用不動産を活用する方法が一般的で、小口化商品以上の節税効果が期待できます。不動産を他人に賃貸することで相続税評価額が取引価格の3分の1ほどになります。
なお、投資用ではない不動産の場合でも、不動産小口化商品と同程度の相続税の節税効果が見込めます。
運用の手間がかからない
投資家がすべきことは不動産小口化商品を選び、出資することのみで、その後の運用は運営会社に任せることができる点もメリットとして挙げられることがよくあります。
ただし、不動産小口化商品の運用にかかる手間はREITと同程度です。現物不動産投資でも、信頼できる不動産管理会社に管理を任せ、需要が高く管理の手間がかからない物件を選べば、ほとんど手間をかけることなく、投資を継続することができるでしょう。
不動産小口化商品のデメリットとは?
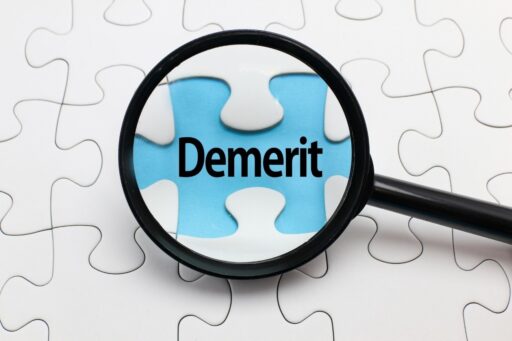 不動産小口化商品のデメリットについて解説します。
不動産小口化商品のデメリットについて解説します。
途中解約ができない商品が多い
不動産小口化商品は運用期間中の解約ができないものが一般的です。中には、第三者譲渡ができるものもありますが、一般的に手数料がかかります。このように、運用期間中に資金が必要になっても現金化できない場合が多いため、必ず余裕資金で投資を行う必要があります。
運用会社の倒産リスクがある
運用している会社が倒産すると、資金が戻ってこない点も不動産小口化商品の大きなデメリットです。投資なので元本保証はなく、倒産しなかったとしても、運用がうまくいかなかったなどの理由で、利益が出ないばかりか、出資した金額が戻ってこない可能性もあります。現物不動産投資のように、運用に失敗しても不動産が手元に残ることもありません。運用会社の倒産リスクはREITにも共通するリスクですが、不動産小口化商品はREITよりも信用度の低い会社が運営しているケース多いため、非常にハイリスクといえるでしょう。
借入を利用できない
投資を行う上で、借り入れを利用してレバレッジを効かせることができないという点もデメリットです。借入を利用できないため、住宅ローンに付随する団体信用生命保険を活用して、保障効果を得ることもできません。前述のとおり、流動性リスクや倒産リスクなどが高いため、必ず余裕資金の範囲内で行うことが重要です。
選択肢が少ない
そもそもの商品数が、売買されている現物不動産の物件数などと比べて少ない点もデメリットです。一定以上の信用度・実績を有する不動産小口化商品となると、さらに数は限られます。自分にあった商品を見つけるためには、選択肢が少ない不動産小口化商品のみで比較するのではなく、他の商品にも視野を広げて検討することが大切です。
なぜ不動産小口化商品は危険・ハイリスクといわれるのか?

なぜ、不動産小口化商品は危険だ、ハイリスクだなどといわれることが多いのでしょうか。不動産小口化商品の危険性・リスクについて解説します。
実績に乏しい企業が運営している不動産小口化商品が多いため
不動産小口化商品の販売は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を得た不動産特定共同事業者(一定の要件を満たす場合は届け出のみでOK)でないと行えませんが、2017年の法改正以降、新規参入がしやすくなったこともあり、不動産小口化商品を販売している業者の中には無登録の業者や架空業者も複数まぎれているといわれています。正しく許可を得ている業者であっても、不動産小口化商品の運営会社は中小のベンチャー企業が多いため、倒産リスクや事業の破綻リスクは必然的に高くなります。
どうしても個人では買えないようなビル等に出資したい場合は、大手不動産会社が主体となって運営しているREITなどを検討したほうが、リスクを抑えつつ安定した投資が行えるでしょう。
高配当を謳った投資詐欺に近い商品も存在するため
すべての不動産小口化商品が該当するわけではありませんが、実際に行政指導を受けた事例、典型的な詐欺手法であるマルチ商法・ポンジスキームに近い実態にあるとされる商品などが複数報告されています。
その特徴は、SNS・有名人を使って勧誘するもの、相場よりも高い利回りを謳うもの、元本保証を謳う(出資法違反)ものなどが挙げられますが、詐欺の手口は年々巧妙化しているため、一見そのように見えないものも少なくないでしょう。
詐欺ではなかったとしても、新しい商品のため、実績が乏しく、広告等で謳われているような高利回りが長期的に続く保証はありません。
J⁻REITや運営母体が国内大手企業のREITでも、利回りは年4~6%程度です。不動産小口化商品にはそれらよりも高い利回りを謳っている商品も多いですが、本当に運営企業にそれだけの利回りを出せる力や実績があるのか、事前によく調べるようにしてください。
十分なリスクの説明なく販売されているケースが散見されているため
メリット強調の広告によって集客し、リスクについての十分な説明なく販売されている不動産小口化商品も少なくなく、リスクを理解せずに購入し、後悔している人も多いといわれています。
不動産小口化商品に限らず、投資には必ずリスクがあります。どのような投資用品を選ぶとしても、必ず購入前にリスクやデメリットを理解するよう努めましょう。
デメリットやリスクをよく理解して投資を行おう
不動産小口化商品は、少額から不動産に投資できる、相続税対策になるなどの謳い文句で募集されていますが、メリットに目がくらんで、非常にリスクの高いとされる商品であるということを忘れてはいけません。
今回紹介した不動産会社小口化商品に限らず、投資で失敗したくないと考える人は、投資判断をする前に、その商品のメリットだけでなく、デメリットやリスクもよく理解するよう努めましょう。
ジーイークリエーションでは、今回解説した不動産投資以外にも、生命保険の見直し、NISAやiDeCo、年金対策、相続税対策など、幅広い相談を受け付けています。
◇下記URLより無料の個別相談をお申込みいただけます。お気軽にお申込みくださいませ。
